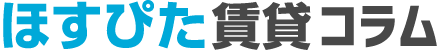「主治医」とは?担当医やかかりつけ医とはどう違う?

主治医やかかりつけ医、担当医など、医師の呼び方はいくつかあります。
どれも呼び方が似ている印象を受けますが、実際に同じ意味なのでしょうか。
この記事では、主治医とはどのような医師を指すのか、かかりつけ医や担当医とは違うのか、それぞれどのような存在なのかなどを詳しく解説します。
また、主治医・かかりつけ医を持つメリットや探し方もご紹介するので、日頃医療機関を訪れる機会のない方も、ぜひ参考にしてみてください。
賃貸スタイルの「住まいの紹介サービス」では、お部屋探しのご相談をLINEやチャットで24時間受け付けております。
通院やご家族の付き添いのために、医療機関の周辺でお部屋探しをしている方はぜひお気軽にご活用くださいね。
主治医とは?

厚生労働省では、主治医の定義を「専門の医療機関と連携をしながら診療所や中小病院で継続的かつ全人的に医療を提供する医師」としています。
さらに、主治医機能として以下の点を期待しています。
- 複数の慢性疾患を診る
- 通いやすい場所にある
- 継続的に服薬管理や健康管理をおこなう
- 必要に応じて専門の医療機関と連携する
複数の慢性疾患を持つ患者は少なくありません。
主治医はそれぞれの慢性疾患に関する専門的な医療機関と連携しながら、継続的な服薬管理および健康管理をおこなうのが望ましいとしています。
また、継続的な医療を提供できるよう、患者が通いやすい場所に位置する医療機関であることも重要です。
上記の項目以外にも、在宅医療の24時間対応も期待されています。
専門の医療機関と連携するため患者を診るのは主治医だけではありませんが、主治医は対象の患者をサポートするチームのリーダー的な存在です。
※出典:
外来医療(その3)<主治医機能について>│厚生労働省
かかりつけ医とは?
主治医と混同しがちな言葉が、かかりつけ医です。厚生労働省では、かかりつけ医とは以下の項目に当てはまる医師と定義しています。
- 健康に関することを何でも相談できる
- 必要な時は専門の医師・医療機関を紹介してくれる
- 身近で頼りになる医師
かかりつけ医は、医師から提案されて決めるものではありません。
自分が「相談しやすいな」「この先生なら信頼できる」と感じた医師を、かかりつけ医として選べます。
さらに、かかりつけ医は診療科を問いません。
眼科のかかりつけ医、耳鼻科のかかりつけ医など複数のかかりつけ医を持つことも可能です。
定義をみると主治医と似ていますが、主治医は患者をサポートするチームのリーダー的存在であるのに対して、かかりつけ医はほかの専門医や医療機関を紹介してくれる窓口的な存在でもあります。
担当医とは?
担当医とは、主治医が率いるチームの一員として患者を治療する医師のことです。
主治医はチームの責任を負う立場、担当医は直接患者を治療する立場とイメージするとわかりやすいかもしれません。
なお、担当医は治療ごとに異なるケースがあったり、複数の医師が治療を担当したりするケースもあるため、変わることもあります。
一方、主治医は基本的に治療が終わるまで変わらず、主治医と担当医の両方を担うケースも多いことが特徴です。
主治医やかかりつけ医を持つメリット
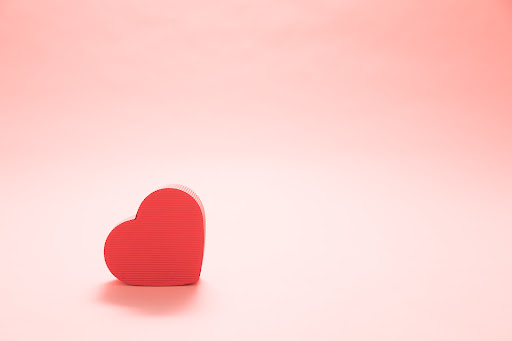
主治医とかかりつけ医の定義は厳密にいうと違います。
しかし、どちらも「持病や体調不良のときにいつも診てもらっている先生」との意味で、同じように使われるケースも。
主治医やかかりつけ医を持つと、健康に関する安心感を得られるメリットがあります。
気になることをすぐに相談できる
主治医やかかりつけ医がいるのは、基本的に通いやすい場所にある医療機関です。
「体調がいつもとちょっと違う気がする」など、何かあったときにすぐ相談しに行ける医療機関が近所にあるのは大きなメリットです。
症状が軽いうちに相談すれば、万が一病気にかかっていても早期発見・治療を開始できる可能性もあります。
また、自分の健康状態を把握してもらえているだけでなく、普段から健康に関する相談をしている医師になら、家族の健康も相談しやすくなります。
的確な診断やアドバイスがもらえる
主治医やかかりつけ医は、これまでの病歴や現在治療中の病気に関する状況、体調など、自分の健康に関する情報を把握しています。
気になることがあった場合でも、健康に関するこれまでの情報をもとに、的確な診断やアドバイスをしてもらえるでしょう。
また、気になる症状が現れた際は、周囲の方に相談したりインターネット検索したりする方法もありますが、それだけで不安は解消されませんよね。
知識のある主治医やかかりつけ医に診断やアドバイスをしてもらえれば、安心感も得られます。
専門医療機関を紹介してもらえる
診察を受けたうえで、専門的な治療や入院が必要になった場合は、適切な治療が受けられる医療機関を紹介してもらえます。
もちろん、初めて受診した病院でも、専門的な医療機関での治療が必要な場合は紹介状を書いてくれます。
しかし、これまでの健康に関する情報は患者本人から聞く内容しかわからず、大きな病院での受診が必要になった際は診察や検査を一からしなければなりません。
一方、これまでの状態を把握している主治医やかかりつけ医なら、紹介先に医師目線での情報を的確に伝えられるのでスムーズです。
主治医やかかりつけ医を探す方法

持病がない、特に気になる症状もなく医療機関を受診する理由がないなどの場合は、健康診断などで医療機関を訪れる機会に主治医やかかりつけ医を探しましょう。
健康診断・予防接種
日頃から健康で、病院やクリニックを受診する機会がない方は、健康診断や予防接種で訪れる医療機関や医師を候補にしてみる方法があります。
健康診断や予防接種の問診などで医師と接した際、話や相談がしやすいかどうかなどをチェックしておくと良いですよ。
本格的に探したい場合は、健康診断と予防接種を違うところでおこなうなど、何ヵ所か別々の医療機関で受診してみましょう。
家族の受診
家族が医療機関を受診するときに同席するのも一つの方法です。
例えば、定期的にかかりつけ医を訪れる親の付き添いをするなどして、その医療機関や医師をチェックしておきます。
自分は受診をしたことがなくても、診察の様子や話しやすさなどを見たことのある医師なら、初対面の医師よりは安心できるでしょう。
産業医に相談
職場に産業医がいる場合は、産業医面談などを通じて医療機関を紹介してもらう方法があります。
産業医は基本的に治療行為はおこなわないため、何らかの症状があっても治療してもらう医療機関は自分で探さなければなりません。
しかし、さまざまな医療機関を知っている産業医なら、症状に応じて適切な医療機関や受診すべき診療科のアドバイスをしてくれます。
まとめ
主治医とは、患者をサポートするチームのチームリーダーのような存在の医師です。
通いやすい場所にある医療機関で、継続的にその患者の治療をおこないます。
かかりつけ医も健康面で気になることがあるときに相談できる点は同じです。
主治医やかかりつけ医を持っていれば、何かあるときにすぐ相談できますし、的確なアドバイスをしてもらえます。
医療機関を受診する機会のない方も、いざというときに安心して受診できるよう、主治医やかかりつけ医を探しておくのがおすすめです。