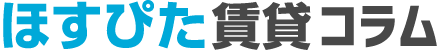「申し送り」とはどういう意味?看護師向けに正しい使い方や例文もご紹介

申し送りは、看護師や介護士、警備員などシフト制で勤務をする職種では重要な業務です。
交代時に、業務内容や進捗、状況などを正確かつ的確に把握する必要があるためです。
特に入院病棟などで働く看護師にとっては、患者の情報を引き継ぐための大切な業務です。
この記事では、看護師にとっての申し送りの意味や目的、正しい使い方や例文を紹介するので参考にしてください。
賃貸スタイルの「住まいの紹介サービス」では、お部屋探しのご相談をチャットで24時間受け付けております。
就職や通勤のために、医療機関の周辺でお部屋探しをしている方はぜひお気軽にご活用くださいね。
申し送りとは?意味や目的、方法を解説

はじめに、看護における申し送りの意味や目的、方法や必要性を紹介します。
申し送りをする職種は複数ありますが、ここでは看護師がおこなう申し送りの特徴を詳しく解説するので、参考にしてください。
申し送りとは?申し送り事項と業務内容
仕事における申し送りとは、勤務交代時に次の勤務者に内容や状況を伝えることです。
看護師だけでなく、介護士、警備員など24時間体制で交代で仕事をする職種では、申し送りは重要な業務です。
申し送りの際に伝える事項は、職種によって異なりますが、主に仕事の進捗、継続している仕事の状況などです。
看護師ならば、担当している患者さんの容体や、本日の検査などを申し送りで伝えます。
一つの仕事を複数の担当者でおこなう際、しっかりと申し送りをしないと思わぬミスにつながる危険性があります。
看護における申し送り業務とは
看護師における申し送り業務は、交代制勤務を導入している病院や介護施設などで実施されます。
勤務交代時の申し送りの内容は患者の状態や状況が主ですが、イレギュラーな事態が起こった場合は、その旨も伝えられます。
また、手術室、検査室などで患者を移送するたびに病状や状態を伝えるのも申し送りです。
したがって、手術をする患者さんやいくつも検査をする患者さんの担当になると、1日何度も申し送りが必要になる場合もあるでしょう。
看護師側から見れば何度も同じことの繰り返しのように思えるときもありますが、医療ミスを防ぐためにも申し送りは欠かせません。
厚生労働省の資料によると、総業務時間における各業務時間の占める割合で看護師間の申し送りは労働時間中に割く時間が4番目に多いとのことです。
看護の申し送りの主な目的
看護業務における申し送りの主な目的は、以下のようなものです。
- 担当医からの指示・患者の状態・注意事項などを正確に伝えるため
- 患者さんに継続した良質の看護を継続して提供するため
- 検査や処置に間違いが起きないようにするため
- 患者さんの要望を伝えるため
入院患者が多数いる病棟勤務は、看護するスタッフも複数必要です。
情報の引き継ぎが正確におこなわれないと患者さんに良質な看護が提供できないのはもちろんのこと、医療ミスにつながる恐れもあります。
申し送りと引き継ぎの違いとは?
申し送りと引き継ぎは、自分が持っている情報を他者に伝えるという点では同じです。
ただし、申し送りは毎日の業務ですが、引き継ぎは前任者から後任者へ仕事の内容を伝えることを指します。
例えば、新人教育を担当していた看護師が交代する際、マニュアルやノウハウを後任に伝えるのが、引き継ぎです。
引き継ぎはイレギュラーな業務といえますが、申し送りよりも引き継がれる内容が多いため、さらに時間をかけておこなわれることも多いでしょう。
申し送りのコツやポイント

申し送りは毎日の業務ですので、できるだけ効率的に済ませたいと考える方も多いでしょう。
しかし、スピードだけを重視すると伝えるべきことが伝わらず、医療ミスの要因になりかねません。
ここでは、申し送りを効率的におこなうコツやポイントを紹介します。
メモを取り、書面と口頭で伝える
勤務中に起きたできごとや患者さんの様子、担当医師からの指示などは、メモを取っておきましょう。
仕事が忙しいとなかなか難しいかもしれませんが、メモを取るという行動で、要点がまとまります。
また、申し送りの際にメモを元に書面で渡して口頭で補足すれば、理解度も深まります。
走り書き程度のメモでも、必ず伝えなければならないことを忘れないようにできるメリットがあります。
項目別に情報を整理する
申し送りをする際は、以下のような情報を項目ごとにまとめて整理しましょう。
- 患者の状態
- 患者やその家族からの要望
- 医師の指示や変更点
- 注意点、指示待ちの項目
全て一から制作するのも大変なので、記入シートのテンプレートを作っておくと記入時間の短縮にもなり、職場全体で使いやすくなるでしょう。
記入したメモは一定期間残しておくと、誰からの申し送りかもわかります。
さらに、複数人で確認すれば情報を間違って伝えたり、伝え忘れたりするのを防げます。
事実と推測を区別する
申し送りをする際は、事実と憶測は区別しましょう。
例えば、医師からの指示があった、というのは事実です。
しかし、指示をしたのはこういう理由なのだろう、だから先回りしてこういうことをしておこう、と判断するのは憶測です。
憶測を伝えるのは決して悪いことではありませんが、区別しなくてはいけません。
申し送りをする際は、まず医師から指示があったことを事実として伝えてください。
次に、「これは私からの意見ですが」と前置きして憶測を伝えれば、申し送りをされる側も混乱せずにすみます。
ケース別の申し送りの例文を紹介

最後に、ケース別申し送りの例文を紹介します。
申し送りの際にいつも悩みがちな方は、参考にしてください。
入院中の患者用の申し送り例文
入院中の患者を担当する場合、申し送りをする際に以下のようなことを伝えます。
- 患者の現状
- 治療や処置などの状態
- 医師からの指示や変更内容
- 患者や家族からの要望
これらの情報をふまえた例文は、次のようになります。
「A号室のBさん、○日○時、手術の準備のため、Cの投薬を開始しました。
開始から現在まで、大きなトラブルはありません。
また、手術後はDの投薬が開始になります。
Dは手術後に薬剤部から届くとのことですので、意識が回復されたら投薬の説明をお願いします。」
新規の入院患者用の申し送り例文
新規の入院患者を担当した場合は、申し送りで以下のような内容を伝える必要があります。
- 氏名や年齢、性別など、個人情報
- 担送か護送、独歩などの移送区分
- 病名、主訴
- アレルギーの有無
- 既往歴の有無
- 現病歴と現在の病状
- インフォームドコンセントの内容
- 医師からの指示内容
これをふまえた例文を紹介しますので参考にしてくださいね。
「本日00時、A号室にBさん(00歳・男性)が入院しました。
病状はDで、Eの検査を受けるのが目的です。
独歩は問題なく、アレルギー、既往歴ともにありません。
明日の検査Eに向け、食事制限と飲水制限の指示があります。」
まとめ:効率的で効果的な申し送りをするために
申し送りは毎日おこなわれる業務ですが、忙しい時間帯にしならない場合も多く、効率化が求められるケースもあるでしょう。
テンプレート付きノートを用意するなど、短時間で的確に申し送りをする方法を考え、できることから実施していきましょう。
申し送りが的確にできるようになれば、良質の看護が提供できるだけでなく医療ミスの予防にもなります。